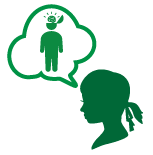ピクセル
監督 クリス・コロンバス
出演 アダム・サンドラー ミシェル・モナハン
制作 2015年 アメリカ
パックマンが登場
(2016年02月13日更新)
- 昔の話。まだ、歩行者天国とかがそこらにあったころ。 大阪は淀川区にある、豊中の境に位置する三国駅を降りてすぐに、ダイエーというスーパーがかつてはあり、信号を超えると長いアーケードの商店街がある。 大阪という町はアーケードの商店街が多く、その規模はアーケードの外の路地にまで広がる。 さすがは商人の街だが、そこに少しの色恋のにおいがしたりして、大人と子どもが入り混じった街を形成していた。 三国駅近くのアーケードの外にも、酒屋や一杯飲み屋みたいなものも軒を連ね、その狭い路地の一角にもそれなりに町の活気があった。 そんな商店街からすぐの場所にあった酒屋跡に、ある日電子音が聞こえるようになる。 暗い店の中は、裸電球のような小さな明かりが天井にあるだけで、後はテーブル上の機械の明かりが店内に灯をともしていた。 アーケードゲームと呼ばれるその機械を、当時の子どもたちは歓喜で受け入れた。 僕たちの憧れのゲームは、当時大流行していたドンキーコングやパックマンというゲームで、今思えば同じ画面の繰り返しで、単純なものではあったが、スティックで操作されるゲームの主人公に、子どもたちは夢中でゲームに興じる。 やがて時は過ぎ、単調な繰り返しを脱するように、小学校4年生の時にはゼビウスという、シューティングゲームが一世を風靡する。 ゼビウスは基本ステージが十数面まであり、隠れキャラや、イベントなどもあり、当時としては画期的なリズミカルな音楽も定評があった。 僕たちは立ち台と呼ばれるアーケードゲーム機の前で、五十円玉を並べて、腕を競い合った。 全面クリアを何回できるのかを友達と競い合ったりもした。 行動範囲が広がると場所を変えて行くようになった東三国駅の近くにあったガレージを改装した店内では、朝から出かけ、昼はそこでカップラーメンを給仕してもらい、それこそ夕方までゲームに興じた。 親が仕事で忙しかったのをいいことに、僕はそこで、お小遣いが無くなるまでゲームに明け暮れたりした。 今思えばなぜそんなにもゲームに夢中になったのかわからない。 僕は小さな箱の中に広がる狭い世界に閉じこもっていたように思う。 ただ漠然とあった思いとしては、その箱の中で繰り広げられる世界では、自分の腕を磨けばいくらでも向上していくことができる。 やりこめばやりこむほど結果が出た。 そういった成長の楽しさがあったのだろうか? もう少し大きくなり、隣の中学校区まで足を伸ばすと、そこの校区の子どもと喧嘩になる。 当時はゲームセンターは不良のたまり場でもあったので、カツ上げや小競り合いがよくあった。 僕は争いは嫌いだったので、あまり別の校区に足を運ぶようなまねはしなかったのだが、それでも同級生の喧嘩のうわさは聞いていた。 やがて高校生になり、ゲームセンターには行かなくなる。 もっと楽しいものが世の中にあることを知るようになる。 そしてもう少し大人になり、たまに行くゲームセンターでは様変わりし、一見してもゲームのプレイ方法もわからなくなってしまっていた。 子どものころ夢中にやっていたスコアが右上に出るインベーダーや、ディグダグのようなドット絵のピクセル画像は姿を消し、リアルと体感がゲームセンターを覆っていた。 ゲームセンターにあったワクワクしたあの高揚感は消え去り、リアルが追及されていく姿に、ただただ感嘆するだけだった。 最近は子どもも小さいのでゲームセンターにも行くようになった。 子どもはそんなゲームの変遷など知らないので、僕がやる古いゲームコーナーの1942というシューティングなんかを横で見ながら、楽しそうに目を輝かせて見ている。 自分の子どものころと変わらないものだなあ、なんて事を思うと自然とうれしくなる。 ゲームは大人と子どもが心を通わせることができる、数少ないものではないかなあと思うわけである。 ということで今回の映画紹介は、パックマンが登場する「ピクセル」である。 映画は、荒唐無稽なSFなのだが、ただただパックマンを子どもと一緒に見たくて借りた。 ゲームセンターでは今でもパックマンは現役である。(2016/02/11) ドンキーコングも子どもたちは知っている。 30年の時を経て、認知される文化がこの世にどれだけあるだろうか。 ゲームは時代を追って変わっていく。 しかしその本質は今も変わらない。 今回紹介する映画「ピクセル」の主人公はゲームで人生が前に進めなくなっていたが、最後はゲームに感謝する。 映画自体はコメディで荒唐無稽で、馬鹿馬鹿しいのだが、ゲームという文化を取り上げる物語としては、さもありなんな感じではある。 パックマンの開発者のそっくりさんが登場するくだりは、なぜ登場したのかは知らないが、アメリカっぽかったです。 個人的にはゲームの主人公に恋するオタクとキスシーンをした女優さんが、ひどく気の毒でした。
■広告